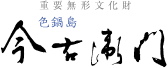色鍋島と今右衛門の現代 (1)
この文章は2006年雑誌「炎芸術 No.86」にて14代今右衛門がインタビューを受けた内容です。
インタビューその1
「色鍋島」で重要無形文化財保持団体の指定を受けている有田の名窯。今右衛門窯の第十四代を、今泉雅登氏が襲名してはや4年が過ぎ、窯元のリーダーとして、また陶芸家・今泉今右衛門としても、近年非常に充実した仕事を見せている。
色鍋島の世界に「現代性」を強く打ち出し、革新的であった父・十三代今右衛門(人間国宝)の名声と名窯「今右衛門」当主という重責に押しつぶされることなく、十四代ならではの世界が拓かれようとしている。
色鍋島のみならず、日本の色絵磁器において、新しいかたちでの「伝統」と「現代」の融合を追及しようとする十四代に、その意気込みを聞く。
十四代今泉今右衛門襲名
編集部(以下◆)平成14(2002)年に十四代今右衛門を襲名され、翌年から日本橋三越などで襲名披露展を開催されましたね。最初に拝見したときには、40歳という若さでの襲名は大変だろうなということと、いきなりご自身のカラーを出してこられたなという感想を持ちました。襲名から襲名披露展までの1年間は相当苦労されたのでしょうね。
今右衛門(以下◇)平成13年の秋に十三代が亡くなり、翌年2月に十四代を襲名しましたが、十四代としての作品をおみせすることが本当の襲名と思いましたので確かに大変な1年でした。
◆襲名披露展で「墨はじき」という技法を初めて知りましたが、これはどういうことから始められたのですか?
◇「墨はじき」技法自体は、もともと江戸期の色鍋島にあたるものです。素地(きじ)に墨で文様を描いて、その上に呉須を塗って焼くと、墨が撥水剤の役割を果たして、文様が焼き飛んで白抜きになるわけです。
昔、現代陶芸を志していまして、その頃からこの描いたところが白抜きにある反転の発想の墨はじき技法に惹かれていました。
◆現代陶芸というと、たしか武蔵野美大の彫刻のご出身でしたね?
◇いえ、工芸工業デザインの金工専攻です。でも、たしかに金属でオブジェや現代彫刻のような作品を作っていましたが、その頃から金属の素材感ということにも共通して、磁器の石の素材感ということにも興味を持っていました。
◆その後に、走泥社の創立メンバーだった京都の鈴木治さんのところに行かれていますね。やはりあの焼締めの独特なフォルムのオブジェに挽かれたということでしょうか?
◇大学の2年か3年のときに、ある雑誌で鈴木先生の「馬」の作品を見まして、やきものでもこういう世界があるのかと驚きました。それ以来ずっとあこがれていたんです。なにせ当時の佐賀の高校では、美術は印象派ぐらいまでの知識しかなく、東京へ来て、初めて現代美術や現代彫刻に出合ったわけです。
◆90年に有田に戻られて、十三代のもとで色絵磁器の世界に入っていかれますね。オブジェや現代彫刻は「立体」の造形で、色絵磁器では「平面」の絵画に近い絵付けという仕事になりますが、そうしたギャップは感じられませんでしたか。
◇自分の中ではそれほどなかったですね。もの作りというのは、基本的には自分の思いを人にどう伝えていくか、ということだと思っています。その意味では、立体も平面も、さらには文学でも音楽にしても同じだと考えています。
◆さらに言えば、オブジェということでは「工芸」よりも「アート」への志向性がより強いと思いますが、色鍋島という伝統の世界への転向には抵抗はありませんでしたか?
◇逆に言うと、オブジェや現代彫刻というのは、ひとつの価値観を自分で作り上げていく仕事ですね。今までにない価値観で、アーティスト自身が新たな価値観を生み出していくという。
それよりは「色鍋島」というような拠り所となるひとつの大きな価値観があるということの方が、自分の性格にとっては非常にありがたかったですね。
◆有田での色絵磁器の修行時代では、やはり伝統的な色鍋島の様式を写して勉強していくということだったのですか?
◇ええ、最初の頃の仕事は、父に言われて、昔の色鍋島の文様を五寸や七寸の皿に写す、ということを何年もやらされました。
◆そういう仕事をすることによって、色鍋島の様式というものを身体で覚えさせようということだったのでしょうね。
◇実際、父がどのように考えていたかはわかりませんが、父の意図はどうであれ、実際その仕事で、色鍋島の文様、空間の取り方、色鍋島とは何なのかということを勉強できたと思っています。
◆その経験が、いざ自分の文様を作り出そうというときにバックグラウンドとなって生きてくるわけですね。
◇生きてきていると思います。自分の作品でも伝統的なものでも、色鍋島の持っている雰囲気というものが、底辺の力として支えてくれているような気がします。
(その2へ続きます)
(「炎芸術」 2006年No.86号より)