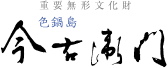雪に見つけた創作の心
江戸時代から続く色鍋島の伝統を、新たな発想を取り入れながら継いでいく。陶芸家として史上最年少で人間国宝となった十四代今泉今右衛門さん。かつて湧き出る思いがないと悩んだ青年は、人の声に真摯に向き合い、自身の作風を築き上げてきた。
大学時代のある冬の夜だった。友人に雪見酒に誘われた道中、ふと電灯の下で空を見上げた。漆黒の闇から、風に巻かれて落ちてくる白い結晶。「降ってくる雪の中心に吸い込まれるような感動を覚えました」。それは単なる美しい風景にとどまらず、今右衛門さんの心の芯に触れるものだった。
子供の頃から絵が好きで、現代美術に憧れて大学では金属工芸を専攻していた。でもデザインへの理解は深まらず、技術も身につかず、成績はクラスの下の方。「何かを生みだしたいのに、自分から湧き出る思いがない。空回りしていたんです」
でも今、自分は雪景色に震えるほど感動している。「ああ、この湧き出る気持ちさえあれば、一歩一歩ものづくりができるんじゃないか」。その光景は今も脳裏に焼き付いている。
後に雪の結晶は、十四代の代名詞ともいわれる意匠となる。墨で文様を描いた上から絵具を塗ると、墨がある部分だけはじかれる。さらに窯で焼くと墨が飛び、白抜きの文様が現れる。「墨はじき」と呼ばれるこの技法で表現される雪は、伝統を踏まえつつモダンな作風として評価が高い。
佐賀県の有田焼を代表する窯元である今右衛門窯は、三百七十年以上の歴史を誇る。江戸時代は将軍家への献上品などとして作られた磁器、「色鍋島」の上絵付けをする御用赤絵師を代々継承。明治以降は全ての制作工程を担う窯元となり、職人集団としても国の重要無形文化財の保持団体に認定されている。赤絵の調合、技術は一子相伝の秘宝として受け継がれてきた。
十三代である父の次男として生まれた。小、中学生の頃は祖母に「男兄弟二人で家の仕事を継いでくれるといいね」と言われていた。だが跡継ぎは代々長男で、当然兄が当主になると思っていた。「責任のある立場は嫌だなあというのが正直なところでしたから、兄への嫉妬もありませんでした。いつか家を手伝おうというくらいの気持ち」
焼き物は帰ってから学べるからと、武蔵野美術大学で金工を専攻。インテリア販売会社に三年間務めた後、オブジェを制作する京都の前衛陶芸家、鈴木治さんに師事する。「父に相談すると『それはいいかもしれん』と。兄が十四代を継いでそれを手伝う立場になったら、次男の名前が全く出ない。だからオブジェを自分の名前で制作するのはよいことだ、と許してくれました」
こんな形の作品を作りたいと、焼いた粘土を削って切り貼りした模型を見せると、鈴木さんは言った。「我々がしているのは陶芸なんやで」。陶芸は焼くときに収縮したり、割れやすかったりと制約が多い。「その中でいかに形にできるかを追求する。人間の力で押さえつけるものではない。鈴木先生は伝統とか陶芸の大切なところをよく理解しながらオブジェを作られていたんだと、だいぶ後になって理解できました」
1990年、今右衛門窯に入った。そのとき、兄の善雄さんは既に父の下で十年間の修業を積んでいた。だから四年ほどたった正月、父が発した言葉は意外だった。「次の代をどうするか。おまえたちふたりで決めろ」
自分はオブジェを作りながら家業を手伝う立場。そう思っていたから一年間、兄と特に話し合うこともなく、次の正月を迎えた。膳を囲む家族一同に兄が切り出した。「作る方は弟に任せようと思う。自分は販売を手掛ける」。虚を突かれ、父がどう答えたのかも記憶にない。「任せるって急に言われても......。でも言い返さなかったです。兄が言った言葉の重さもありますので」
善雄さんの決断は、窯の将来を思ってのことだった。「自分も技術の面では自信がありました。だけど弟は大学でデザインも学び、職人とは違う発想の文様を描ける」
次期当主として、また兄の思いを受けて、何かを生み出さなければならない。作品作りに没頭した。1998年、「墨はじき」の新たな技法で絵をつけた鉢が、日本伝統工芸展で受賞する。梅の花を描いたものだったが、窯から上がったときにふと、雪のように見えた。「雪だったら、学生の時の思い出を表現しよう」
ある染織家から「世界で初めて人工雪を作った中谷宇吉郎さんについて勉強するといい」と教えてもらい、東京・神保町の古書店を探し回って著書「霜の花」を手に入れた。六角形の結晶がシダ状に伸びる様子を新しい文様のヒントにした。父が残した「薄墨」と呼ばれる技法で背景にグラデーションを付けると、吸い込まれるような雰囲気を表現できた。二十年ほどの時間がかかったが、あの夜の雪景色をものにした。
2014年、陶芸家として史上最年少の五十一歳で人間国宝に認定される。父に続く栄誉だった。共に仕事をした十一年間、父によく言われた「伝統は相続できない」という言葉を胸に刻む。伝統とはその時代を担う者が一生懸命取り組んで見つけるものだという教えだ。
歴代の今右衛門の作品をたどると、父の時代に雰囲気ががらりと変わる。十二代までは昔の名品の写しに励んだが、十三代は伝統技法を生かしつつ新たな技術を生み出すことに注力した。「常に移り変わっているという認識を持ち、現代的価値を反映しようと向き合わなければ、伝統は廃れる」
大切にしているのが、人の声に耳を傾けることだ。依頼に応えて新しい文様に挑んだ作品が評判を呼ぶことも多い。「自分の思いだけで作っていると理屈ばって先細りになる。千利休と(楽焼の始祖である)長次郎の関係のように、使い手と作り手の関係で美意識が上がるんです」
人との関わりのなかで、次はどんな文様が見えてくれるのか。あの雪の夜以来、創作への思いは尽きることなく湧き続けている。
日本経済新聞「My Story」2020.04.05 より